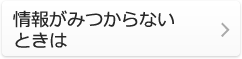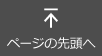とくしまヒストリー ~第21回~
最終更新日:2019年2月8日
「助任」 -城下町徳島の地名9-
「助任」は、城下町徳島のなかでも、「富田」「津田」「寺島」と並んで最も古い地名だ。鎌倉時代初期に名東郡内に成立していた国衙(こくが)領(国司の直接支配下にある土地)に「南助任保」がある。元久元年(1204)に「津田島」とともに立庄されて「富田庄」の一部となったが、立庄の過程で作成された、建仁3年(1203)の「春日社政所下文案」(春日大社文書)に「阿波国名東郡南助任保」と、その地名がみえる。その由来は定かではないが、助任の地名は800年以上前から存在していたのだ。
南助任保の範囲は広く、「東限津田北海、南限八万堺勢因峯(勢見山)・西限名東庄堺、北限吉野河」と、城下町徳島がまるごと収まってしまうほどの広さだった。
天正14年(1586)に徳島城が築かれ、その周囲に城下町が開かれると、城の北方にあたる助任の地に、武家地と町人地が置かれた。江戸時代になると、現在の助任にだいぶ近付く。淡路街道(助任本町の通り)を境に、東側が町人地、西側が武家地であった(絵図)。圧倒的に武家地が広い。
武家地助任の居住者は、享保17年(1732)の「御家中屋敷坪数間数改御帳」(個人蔵)によると、隣の前川と合わせた数だが124人で、富田に次いで多い。住民は、中老や物頭といった上級藩士から新御蔵から扶持米を支給された無足士までと広範だ。助任地区の屋敷の広さは平均633坪で、城下平均より100坪ほど上回る大きさ。武家地助任の特徴は、屋敷が集中し、しかも大きなものが多かったことが挙げられる。
町人地助任は、寛永8年(1631)から同13年(1636)の頃の城下町徳島の様子を表現した「忠英様御山下画図」(国文学研究資料館蔵)でその地名がみえ、すでに成立していたことが分かる。貞享2年(1685)の「市中町数間数並家数」(『阿波藩民政資料』)では、家数は105軒であった。
江戸時代の初めには、藩主やその家族、藩士が消費する青果・蔬菜類や魚貝の調達は徳島城の近くがよいとされ、徳島城の南側で大手口にあたる内町に、八百屋町と内魚町が設けられた。しかし、寛文7年(1667)と延宝3年(1675)の大火の経験から、城の北側にあたる助任町にも魚貝や青果・蔬菜類の取り扱いが許された。17世紀後半には、助任町は内町に匹敵する重要な町に成長したのである。
ところで、吉野川の土手から助任本町を南に向かっていると城山が一直線に見える(写真)。絵図で確認すると助任本町の通り、すなわち淡路街道は、驚くほど真っ直ぐ徳島城に向かっている。これは何か理由があるのだろうか。
徳島藩主の参勤交代は、鷲の門を出て徳島本町の通りを東に進み、福島橋から小舟に乗り、沖洲で御座船に乗り換え大坂に向かった。だから徳島藩主蜂須賀家の参勤交代の道といえば、徳島本町と思っていた。
しかし、江戸前期には、新町川を下って沖洲と津田の間の「津田口」から出航するコースは使わず、現在の吉野川である「別宮口」を利用していたのだ。別宮口は、徳島城を北に進み吉野川に至る「大岡六間屋」という場所を発着点にした。その場所までは助任本町から淡路街道を進んだ。
この道を使ったことは寛永15年(1638)の藩主日記から分かる。2月16日、「殿様(忠英)今日四つ時分(午前10時頃)ニ御帰城被為成ニ付、老中・物頭・中備、其外御家中不残、六間屋まて御迎ニ罷出、御目見へ被仕候」(蜂須賀家文書「日帳」国文学研究資料館蔵)。
大岡六間屋の船着場や助任本町の通りは藩主を迎えに来た家臣や町人たちで混雑したことであろう。到着した藩主一行は徳島城を目指して、淡路街道である助任本町の通りを一直線に進んだ。だから助任は「参勤交代の道」だったのだ。
ただし、寛永16年には福島から乗船するようになったから、その期間は長いものではなかったが、助任は豊臣家、そして徳川家の時代の初めには城下町徳島の玄関口になっていた。その歴史は現在では埋もれてしまっている。
城がどのように見えるか、道がどのようにつけられているか。こうした視点で城下町徳島を見直してみると、埋もれた歴史を発見することができるかもしれない。

「阿波国渭津城下之絵図」徳島城博物館蔵、天和3年(1683)
[絵図解説]
徳島城から一直線に伸びる淡路街道。その先は別宮川(吉野川)。

「吉野川の土手から見た助任本町」
[写真解説]
城山が一望できる。旧淡路街道の道筋。
参考文献
福家清司氏「阿波国富田荘の成立と開発」(『阿波・歴史と民衆』、南海ブックス、1981年)
河野幸夫氏『徳島・城と町まちの歴史』、聚海書林、1982年
『日本歴史地名大系37 徳島県の地名』、平凡社、2000年
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。